

本記事は理学療法士(ランニングトレーナー)&市民ランナーである管理人が投稿しています。
SNSは苦手ですがボチボチ更新してます
X(旧Twitter)
イマリ(@myrunning_imari)
特にInstagramをフォローして応援してくださると嬉しいです!!
当ブログでは記事内でアフィリエイトによる商品紹介、広告(PR)が含まれております。
あらかじめご了承ください。
本記事のキーワード:
マラソン、インターバルトレーニング、スピード持久力
スピード持久力を鍛える

スピード持久力をわかりやすく言い換えると
⇨「ある程度の速いスピードを、できるだけ長く維持できる力(スタミナ)」のこと。

たとえば、100mの全力走が20秒かかるとしましょう。
マラソンであれば、100mを40秒〜50秒くらいかけてゆっくりと走りきるイメージです。
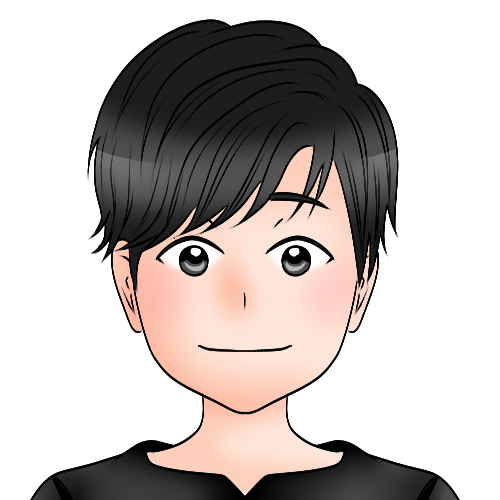
しかし、インターバルトレーニングとは100mを30秒くらいのペースで、1km〜2kmの距離を走りきる⇨少し休憩⇨数セット繰り返し
といったイメージで、心肺機能や足腰に負荷をかけていくといった方法です。
そうすることで【スピード持久力】を向上することができます。
練習方法
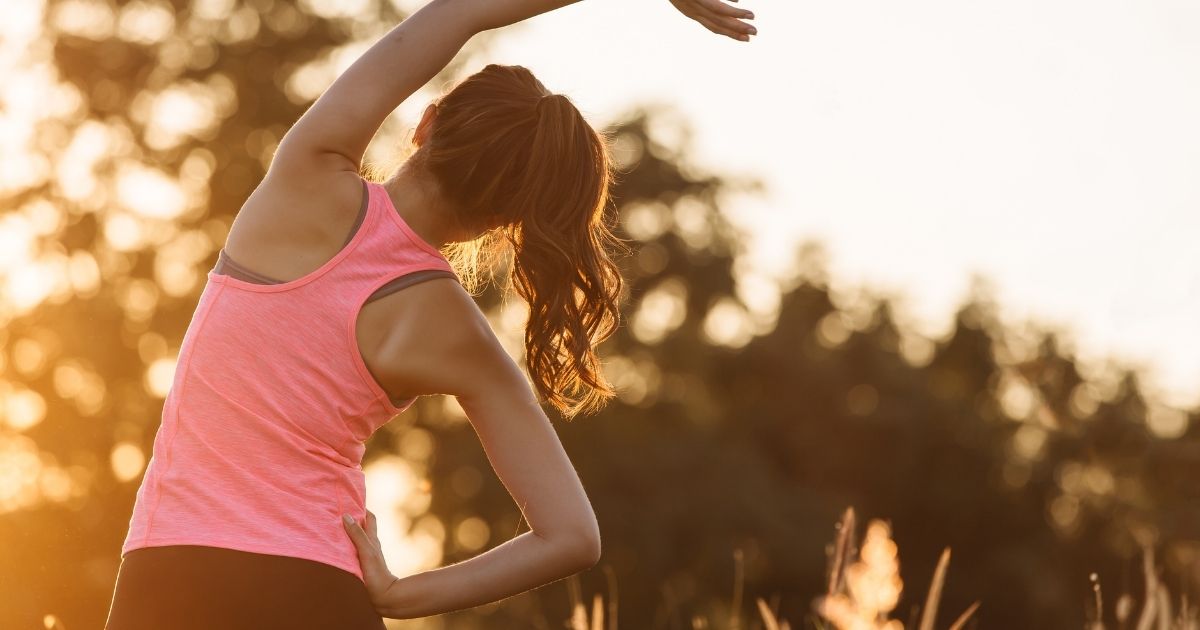
先ほども簡単にイメージを伝えましたが、、
インターバルトレーニングとは
速く走る⇨ゆっくり走る(歩く)⇨速く走る
これを繰り返す方法です。
中学・高校の陸上選手〜大学・実業団のアスリートまで行ういわば常識的なトレーニング方法です。
距離などの工夫はさまざまですが、マラソンを狙うなら最低でも1kmくらいの距離は必要です。
目安となる強度

もちろん人によって適切な量・スピードは違います。
参考にするポイント
- 心拍数
- 疲労感
- タイム
以上の3つです。
心拍数

心拍数の目安をかくにん
(220ー年齢)ー安静時心拍数×50%=【答え】
【答え】+安静時心拍数=【本当の答え】
こちらはリハビリテーションの運動中の目標心拍数を確認する際にも使われる計算式です。
マラソントレーニングには少し物足りない心拍数の目安になることもありますが、それはバリバリ練習できている場合。
初心者であればまずは安全面も考えてこの式で出る数字をひとつの指標にしておきましょう。
※安静時心拍数の計算
⇨運動後などを避けて日常で特に慌ただしく動いていない時間帯に計測します。
楽な姿勢で写真のように手首の下、少し親指寄りの部分で動脈が触れることを確認します。(中指で触れる)
1分間で何回、ドクンドクンと脈を打った回数が安静時心拍数と考えてOK。
(例)僕の場合
(220ー年齢27歳)ー安静時心拍数55回×50%=69
69+安静時心拍数55回=124回
この124回という結果(1分間あたりの脈拍)がインターバルトレーニング中にひとつの指標とする【心拍数】の目安です。
ただあくまでも目安であって、少し控えめな設定でもあるのでしっかりトレーニングを実践すればこの回数は超えてくる可能性は高いです。
きっちりこの回数を守って「目安を超えたからトレーニング中止」というわけではありません。
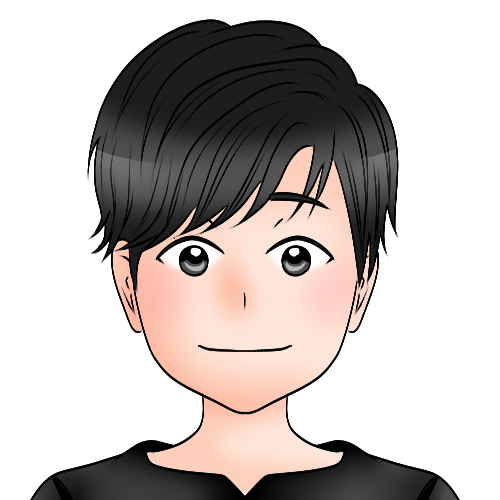
疲労感と設定タイム


と、疑問が出たかもしれません。
そこで代用するのが【疲労感】と【設定タイム】です。
簡潔に伝えると
- 80%くらいの力を使って走る=「ややきつい」という強度
- あらかじめ1kmあたり◯分〇〇秒で走るとタイムを設定しておく
という方法でインターバルトレーニングをこなします。
まずは体験してみよう

実践する順番としてはこちらがおすすめ。
さきほども言いましたが、トレーニング中にいちいち心拍数を図る暇なんてありません。
なので、【疲労感】をメインの指標にして体験してみましょう。
簡単な流れ
- 十分なウォーミングアップ
普段のペースで20〜30分ほどランニング - 400mを全力疾走の70〜80%ほどの力で休まず走る
- 走り終えたら立ち止まらず100mほどゆーっくり走ってつなぐ
- 同じように400mを全力疾走の70〜80%ほどの力で休まず走る
- (2)〜(4)の繰り返し
ポイントは、70〜80%の力で走ること!
まずは、【心拍数】や【タイム】を気にせずやってみましょう。
「結構な力を出してるなあ」と思えるくらいで走るとだいたい70〜80%くらいです。
初めて体験してみると400mって距離は結構ツライですから覚悟しておきましょう。笑
100mのつなぎは【心拍数】を落ち着かせるためのいわば休憩時間です。
これを400m×10本になるまで繰り返しましょう。
余裕があれば、途中で心拍数や400mをどのくらいのタイムで走っているのかタイムを測っておきましょう。
たとえば400mを96秒(1分36秒)のペースで1km走り切るとちょうど4分でゴールします。
これとは逆に目標タイムから逆算して設定タイムを決めておく方法もありです。
フルマラソン3時間30分で完走が目標なら1kmあたり平均4分58秒。
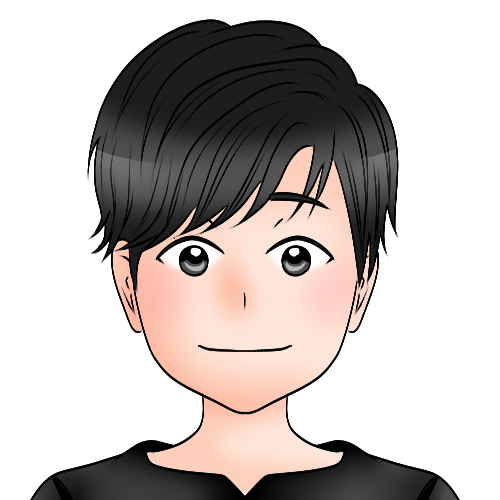
そのために、インターバルトレーニングを通して【スピード持久力】を鍛えなければいけないのです!
慣れてきたら本格的に実践

体験ができたら、次はより本格的なメニューを計画しましょう。
速いペースに設定する距離は最低でも1km以上に設定しましょう。
現状の自己記録(ちから)にもよりますが、ひとつの例を紹介します。
10分間のウォーキング+20分間のラン
(ウォーミングアップ)
↓
(A)2kmラン⇨(B)1kmラン⇨
(A)2kmラン⇨(B)1kmラン⇨(A)1kmラン
(A)は1kmあたり4分30秒〜5分ペース
(B)は1kmあたり8分ペース
(A)で体を追い込み、(B)は休息時間
↓
クールダウン
近くに1周1kmのランニングコースなどがあればそこでも構いませんし、GPS機能付きの時計でシティランで実践してもOKです!
ただし、信号が多い場所や車・人通りが多い場所だと危なかったり走りづらいので要注意。
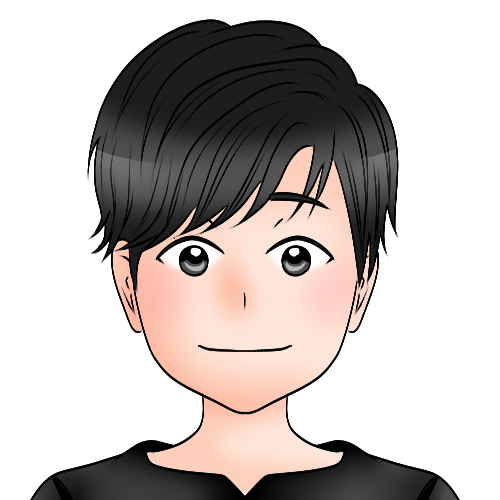
最後に

フルマラソン完走の次のステップは自己ベストタイムの更新です!
そのために必要な練習はハードになります。
できれば週1回、少なくとも月1回以上を目安に仲間と一緒にインターバルトレーニングにチャレンジしましょう。
ポイントは、「心拍数」や「疲労感とタイム」を目安に強度を調節すること。
無理は禁物です。
自己ベスト更新目指してがんばりましょう!!
ランナー向けの栄養補給
練習直後の栄養補給ではカラダの疲労や筋の修復ために「素早いエネルギー補給」と「何の栄養素を摂るか」が大切です。
公式サイトをチェックしてみるとわかるように箱根駅伝常連校の東洋大学や名門実業団の旭化成など多くのランナーが愛飲している製品です。
アミノ酸の配合量がトップクラスという特徴のほかにもビタミンB群がしっかりと入っています。
このビタミンB群はランナーにとって非常に大切な栄養素なんです!!
迷ったらとりあえずコレ!と言えるほどおすすめです。
nosh(ナッシュ)
「NOSH - ナッシュ」![]() はランナーのカラダ作りにおすすめです。
はランナーのカラダ作りにおすすめです。
ハードな練習で疲れた後やトレーニング後の帰宅で遅くなってしまった際にささっと、素早く栄養摂取ができるというメリットがどれだけありがたいことか・・・。
メリット
- 管理栄養士監修で栄養面は心配なし。
- 定期的にメニューが更新されるので飽きる心配なし。
- 注文の回数を重ねるごとに割引が増えてお得になる。
- 冷凍なので長期間保存が可能。
仕事終わり、トレーニング終わりの秘密兵器として冷凍庫に準備しておくと便利ですよ。
ぜひ活用してみてください!
![]()
![]()
ランニング用の骨伝導イヤホンはSHOKz
ランニング中に音楽を聴くことで気分を高めたり、音声サービスを利用して情報収集や勉強時間に充てるのも良いですよね。
しかし、ランニング中は耳を塞いだ状態だと自動車の音などが聞こえづらく、事故に遭う危険性も高まります。
ましてやノイズキャンセリングなんて本当に危険です!!
それを解決してくれるのが骨伝導イヤホンです!!
耳を塞がずに済むので事故の危険性を軽減することができます。
ランニングの時間をさらに有効活用
骨伝導イヤホンと相性が良い音声配信サービスがオーディオブックです。
ランニングは案外長い時間走り続けるので、どうにか時間を効率良く使いたいと思ったことありませんか?
せっかくなら音声配信サービスを使って勉強すれば効率良くランニングの時間を有効活用できますよ。
オーディオブック配信サービス - audiobook.jpと骨伝導イヤホンShokzは相性抜群。
試しに利用してみるだけでもOKです!